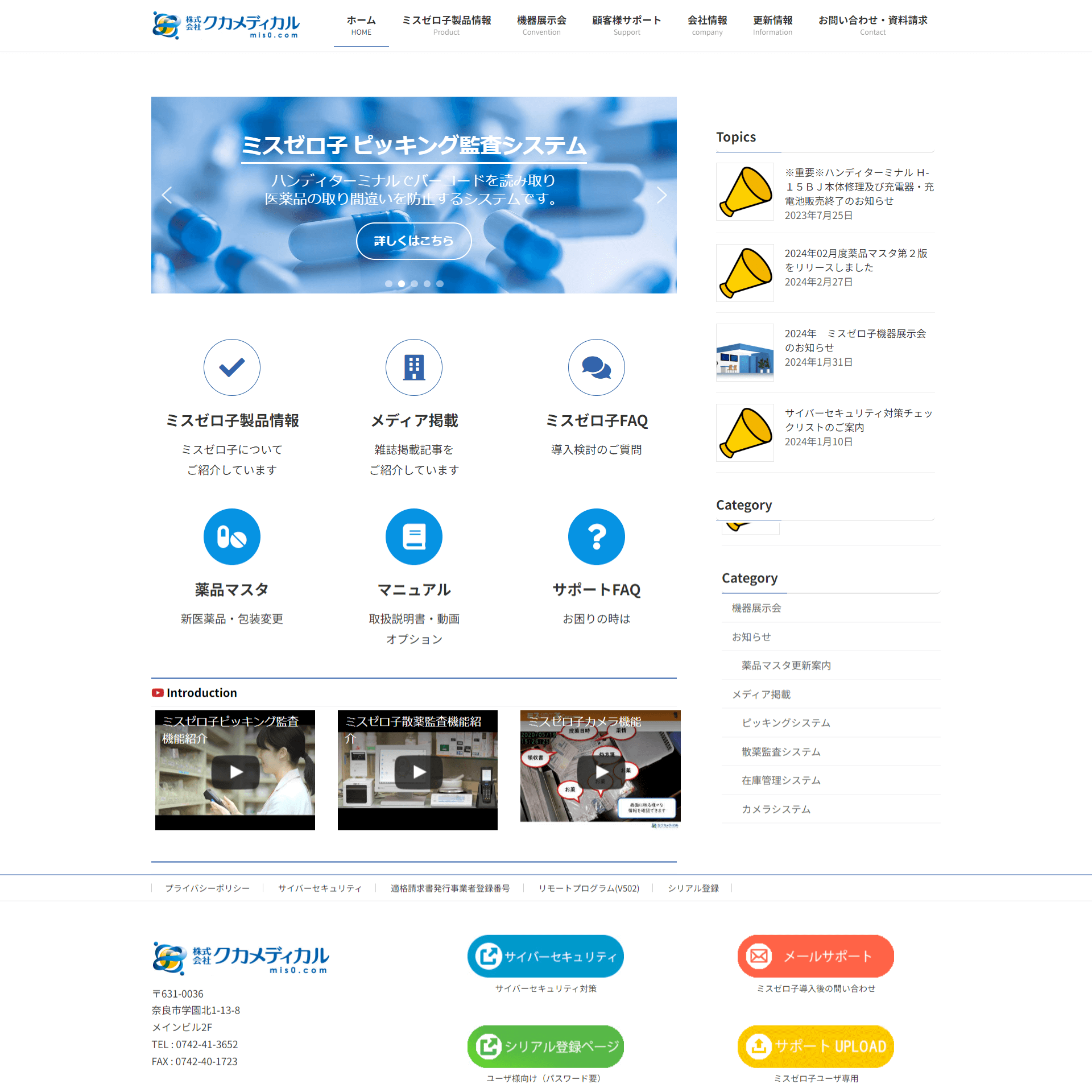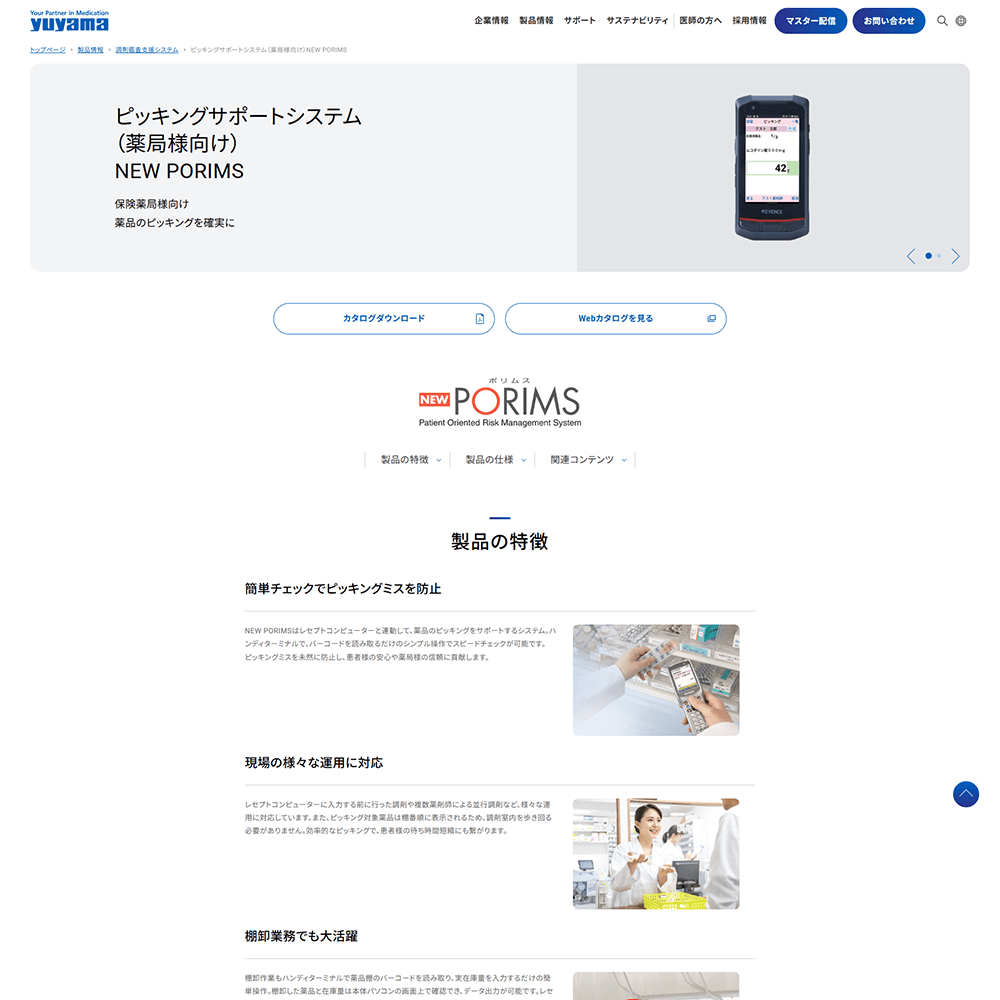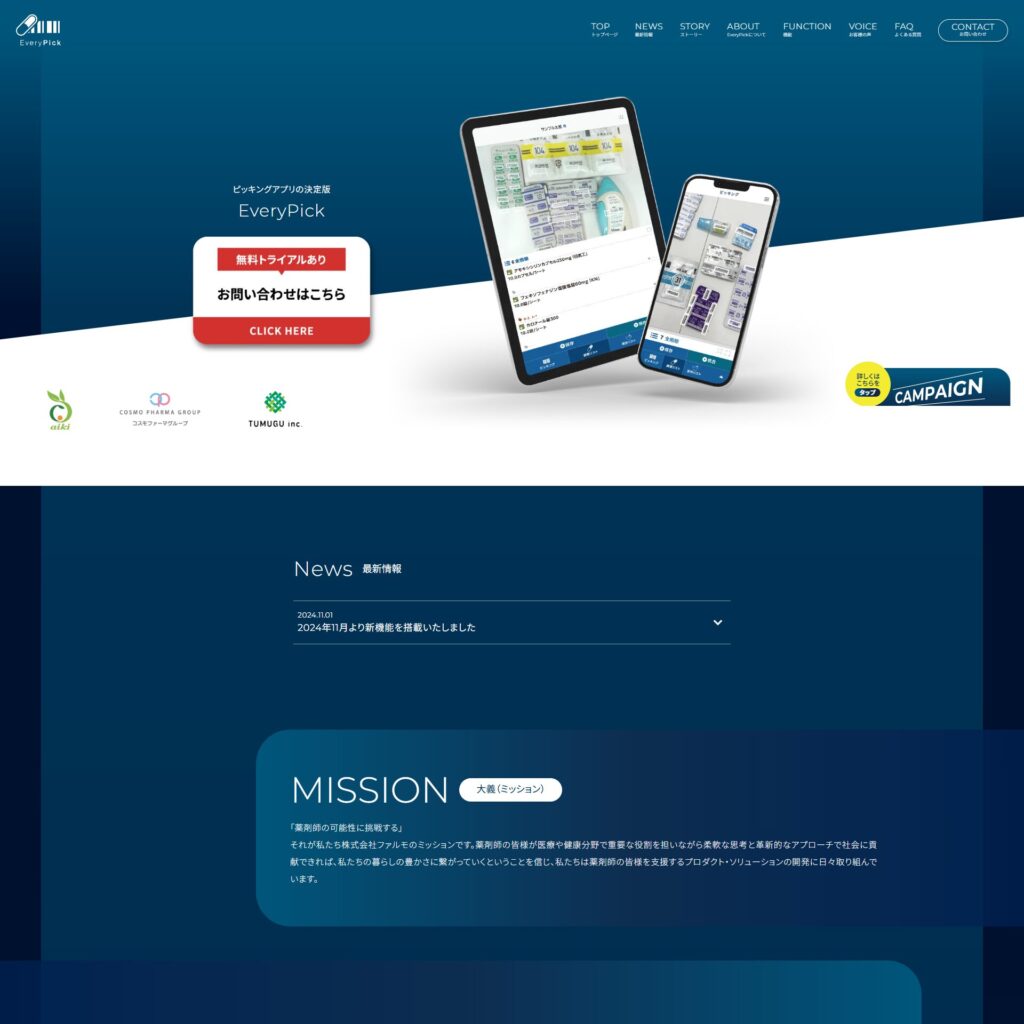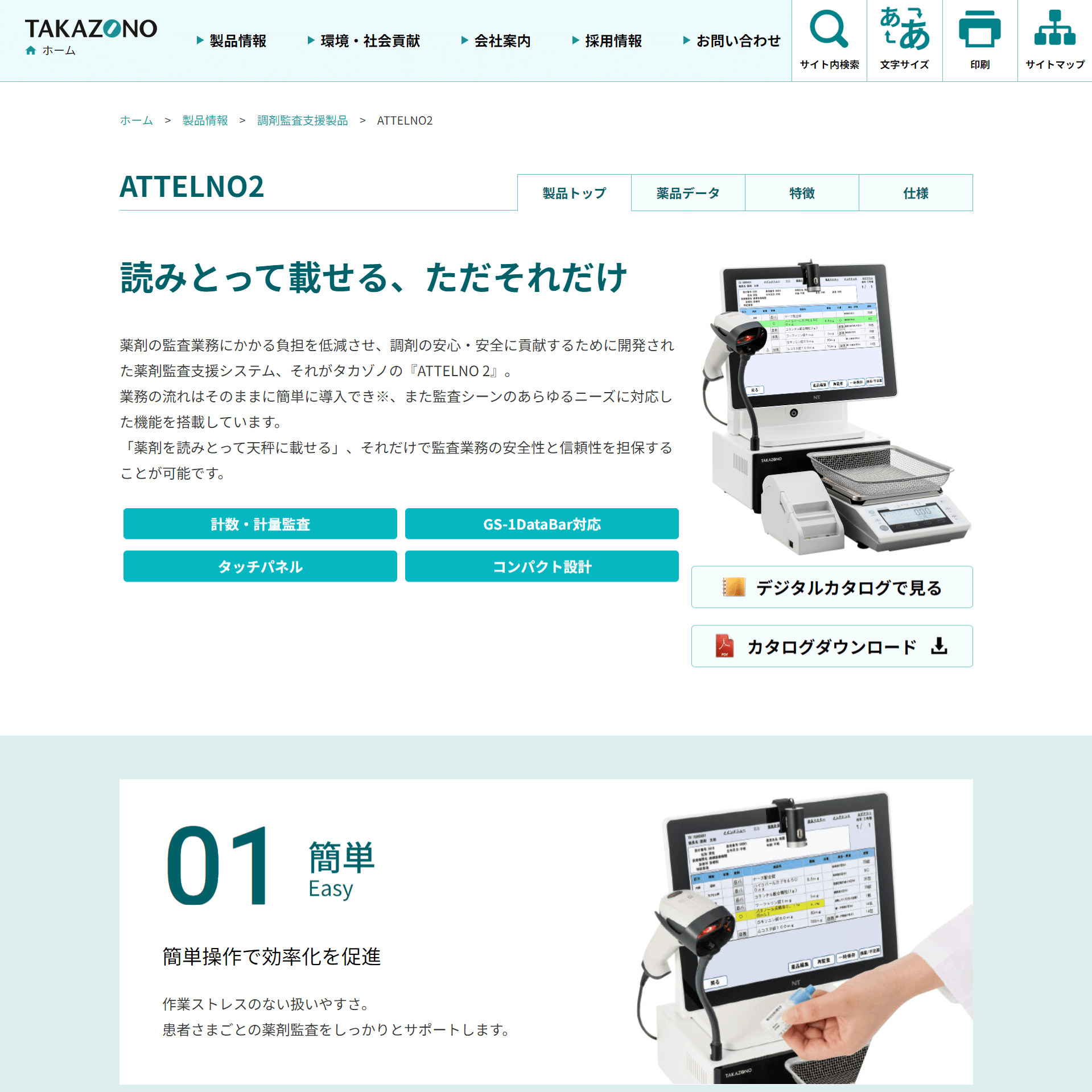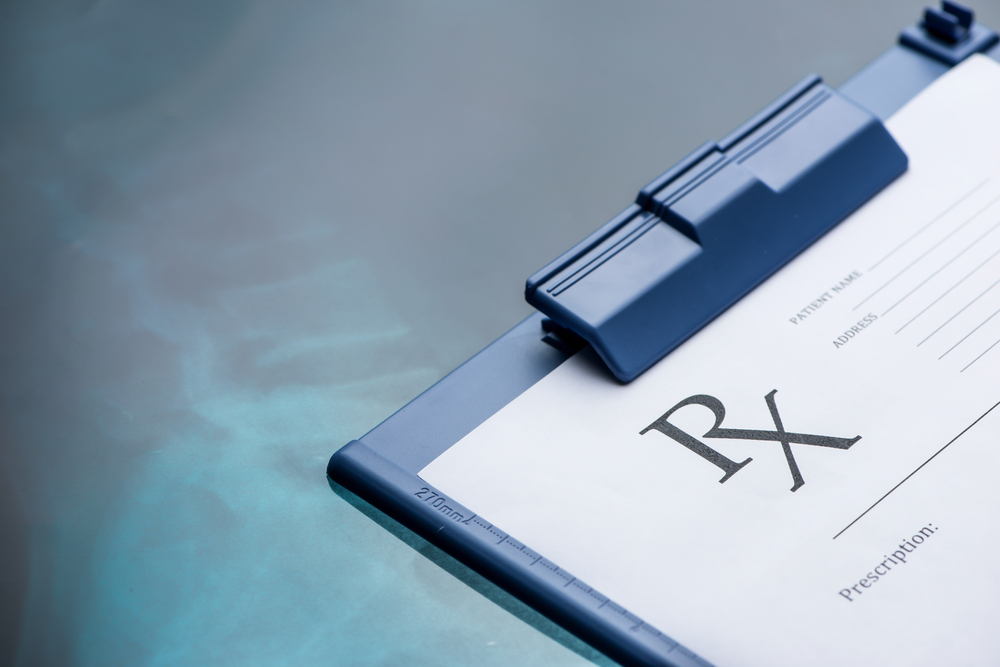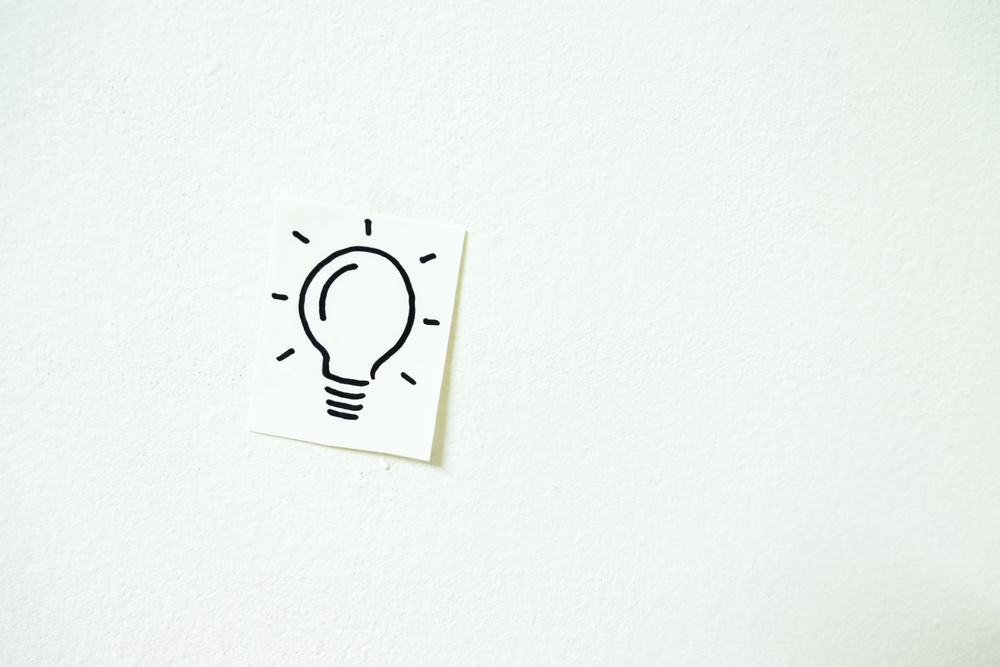薬局の経営に関わるデッドストックについてお伝えします。薬局のデッドストックの廃棄ロスや保管コストが経営を圧迫している、とお困りの方も多いのではないでしょうか。デッドストックが発生する原因を理解して、早急に対処することが重要です。薬局におけるデッドストックの発生原因と処理・管理の方法について詳しく紹介します。
デッドストックとはなにか
薬局の経営に大きな影響を与えるデッドストックについて、詳しく解説します。
デッドストックとは?
デッドストックとは、仕入れたものの処方されることなく使用期限まで保管される医薬品を指します。デッドストックは、使用期限を迎え最終的に廃棄されます。
過剰なデッドストックは、薬局の経営に大きな影響を与えることもあるため対策が必要です。薬局では、処方箋を持参した患者の調剤を拒否することはできないと薬剤師法によって定められているため、処方に対応できるように在庫を余分に抱えている薬局もあります。
処方される量を仕入れることが理想ですが、処方できないリスクに備えて在庫を確保していたり、包装デザインが変更されて旧デザインが残ったり、さまざまな理由でデッドストックが発生します。
医薬品廃棄ロスの損失額
廃棄ロスは、仕入原価だけで完結しません。棚に滞留する間の保管負担や棚卸・使用期限チェックの人的コストに加え、医薬品は一般ゴミとして処分できない場合が多く、専用の廃棄処理費が上乗せになります。見えにくい固定費として利益をじわじわ削る構造と言えるでしょう。
損失の規模感を把握しておくことは、現場の納得感と経営判断をそろえるうえで重要です。薬局一店舗あたりの年間廃棄額は平均で約20万円と推計され、全国約5万9000店でならすと年間100億円規模に達するとの指摘もあります。院内処方まで含めれば、実際の損失はさらに大きくなる可能性があります。こうした実額イメージを前提に、在庫最適化や監査体制への投資を検討していくことが、廃棄ロスの根本的な抑制につながります。
デッドストックが起きる原因
薬剤師法では、処方箋を持参した患者の調剤を拒否することはできない、と定められています。そのため、処方できないリスクや機会損失に備えて在庫を余分に抱えている薬局もあるでしょう。
その他にも返品できなかったり、発注ミスだったり、デッドストックが起きる原因はさまざまです。そのため、発生原因を理解することでデッドストックの対策が可能になります。デッドストックが起きる原因をそれぞれ詳しく解説します。
処方できないリスクに備えて余分な在庫を抱えている
薬局では、薬剤師法によりたとえ在庫がない医薬品を依頼されても処方を拒否できません。そのため、処方に対処できるようにある程度の医薬品を確保する必要があります。
処方される機会が少ない医薬品や患者一人だけが必要な医薬品でも仕入れなければなりません。処方される可能性がある医薬品を用意するため、余分な在庫を抱えてしまうのが現状です。
また、医薬品は100錠などの包装単位ずつの販売になるため、必要な数量以上に仕入れなければならないケースもあるでしょう。包装単位ずつでしか購入できないシステムは、デッドストックが発生する原因のひとつといえます。
開封済みのため返品できない
開封済みの医薬品の多くは、返品できません。医薬品は販売包装単位で仕入れるため、必要以上の在庫を抱えて開封済みの医薬品が余ってしまうこともあります。
しかし、開封済みの医薬品は返品できないケースが多いため、そのまま残ってデッドストックになります。開封済みの医薬品の他にも、使用期限切れや破損、汚損なども返品不可です。
発注ミスなどの人的ミス
発注ミスなどの人的ミスもデッドストックの原因のひとつです。単純な発注ミスの他にもデータの打ち間違いだったり、正確な在庫管理ができていなかったり、誤って必要な数量以上仕入れてしまうことも起こりがちです。
正確な在庫数を把握していない場合には、十分な在庫がある医薬品を発注してしまうこともあるでしょう。徹底した在庫管理や発注データの確認など、しっかりチェックして単純なミスを防ぐことが大切です。
需要予測が外れて消費できない
継続して処方されると予測して仕入れたが、予想が外れてデッドストックになるケースもあります。よく消費されていた医薬品でも、患者の処方やメーカー、1つの錠剤に複数の薬剤が配合されている合剤への変更により、今まで処方されていた医薬品がほとんど消費されなくなる場合もあります。
消費されずに残った医薬品は、デッドストックになる可能性が高いでしょう。
包装デザインの変更
包装デザインが変更されて、旧デザインの医薬品が余ることもあります。旧デザインの医薬品の使用期限が短かったり、開封済みだったり、業者に返品できないとデッドストックになる可能性があります。
デッドストックの処理・管理の方法
デッドストックの保管スペースや廃棄にもコストや手間がかかります。デッドストックは、薬局経営の効率低下にもつながるため、発生が分かり次第早めに対処することが大切です。
デッドストックの処理や管理の方法について解説します。いくつか方法があるため、状況に応じて使い分けることで、医薬品の廃棄ロスやコスト削減につながるでしょう。
系列店で消費する
デッドストックを自社の系列店で消費する方法です。複数の店舗を運営している場合には、系列店同士で在庫状況を共有し、余分な医薬品を必要な系列店に回すことで調整できるためコスト削減にもつながります。しかし、個人経営の薬局では難しい方法だと言えるでしょう。
不動在庫のマッチングサービスを利用する
デッドストックのマッチングサービスとは、デッドストックを抱えている薬局と医薬品の購入を希望している薬局をマッチングさせるサービスです。不要な医薬品を出品したり、交換したり、加盟店同士で取引できるため、デッドストックの解消につながります。
インターネットを経由して売買できるため、手軽にデッドストックを処理できます。デッドストックの解消により、廃棄ロスや保管コストが軽減できるため、薬局経営の利益向上につながるでしょう。
買取専門業者に依頼する
在庫管理を徹底していても、デッドストックが発生するリスクはあります。デッドストックが起きた場合の対処法のひとつとして、専門業者に買い取りを依頼する方法があります。
買取専門業者がデッドストックを一括で買い取り、他の医療機関へ医薬品を販売するシステムです。インターネットを経由してデッドストックをまとめて処理できて現金化もスムーズ。
買取価格は、相場よりも低い傾向があるため注意が必要です。デッドストックの状況に応じて最適なサービスを選ぶとよいでしょう。
デッドストック・廃棄ロスの対策
デッドストックを抑える要は、正確な在庫把握とルール化された運用です。いまある在庫量やロット、有効期限を常時可視化できれば、十分足りているのに再発注してしまうミスは大幅に減ります。滞留の兆しにも早く気づけるため、期限前の融通や購入量の微調整など、先手の対処が取りやすくなります。
近年は在庫管理システムやIoTの導入により、入出庫の記録、需要予測、適正在庫の算出、さらには自動発注まで半自動で運用できるようになりました。データに基づく運用へ切り替えるほど担当者の勘から脱却でき、無駄な在庫と作業の双方を圧縮できます。以下では、この基盤を前提に「見える化 → 標準化 → 平準化 → 監査」の流れで具体策を整理します。
見える化:在庫と期限を一元管理
はじめに在庫の“見える化”を進めます。レセコンや在庫管理機能で在庫量・ロット・有効期限・入出庫履歴をひとつの画面で把握できる状態をつくり、過去の処方実績から需要予測をかけて発注へ反映します。担当者の勘に依存しない運用へ切り替わるほど、期限切迫や重複仕入れの芽を早期に摘み取れます。
標準化:ABC×補充ルールを“強弱”で使い分ける
在庫を一律に厳密管理すると人件費が嵩み、逆にすべてを大ざっぱに扱うと廃棄や欠品を招きます。そこで、品目を金額インパクトでグルーピングし(ABC分析)、グループごとに最適な補充ルールを当てはめる この“強弱”のつけ方が標準化の中核になります。
■ABC分析(品目の重要度を決める土台)
各品目の「年間使用金額(=納入価×年間使用量)」を算出して並べ替え、金額への寄与が大きい少数の品目をA、中核をB、影響が小さい多数の品目をCと位置づけます。Aは在庫資金とロスへの影響が大きいため厳密に、Cは手間を最小化して管理コストを抑える、という運用の指針がここで決まります。季節変動や採用品変更で寄与度は変わるため、四半期ごとなど定期見直しが望ましいでしょう。
■カムアップ(A品目:患者予定から“前倒し確保”)
Aに該当する高額・重要品は、患者ごとの来局予定と処方内容をカード・画面で可視化し、数日先までに必要となる数量を前倒しでチェックします。必要量が在庫を下回るタイミングを早期に捉えられるため、欠品リスクを抑えつつ余剰発注も避けやすくなります。実務ではレセコンの来局予定・継続投薬の情報を活用し、毎日または隔日で直近分を確認すると運用が安定します。
■発注点管理方式(B品目:過不足を防ぐ“しきい値”)
Bは処方頻度が高く金額影響は中程度の群です。ここでは「発注点=リードタイム中の最大消費量+安全在庫」を基準に、在庫が発注点を下回ったら即発注します。安全在庫は期限や供給の揺らぎ、季節性を加味して設定します。ルールが明確なので担当者が変わっても安定運用しやすく、欠品と過剰の両方を抑制できます。
■ダブルビン方式(C品目:低コストで“切らさない”)
Cは低額・多頻度の品目です。二つの保管箱(または二単位の在庫)を用意し、片方が空になった時点で補充をかけ、もう片方でリードタイムを凌ぎます。箱一つ分の基準量を「リードタイム消費量+最小限の安全在庫」で決めておくと、点検も補充判断も瞬時に行えます。記録負担が小さく、人件費のかけ過ぎを防げます。
平準化:店間融通と二次流通で滞留を逃がす
系列店がある場合は在庫を横断で回し、期限が迫る品は意図的に前倒しで消化します。個店で難しいときは、会員制の売買・買取サービスを併用し、廃棄に至る前の現金化を狙います。場当たり的な対応ではなく、平時から“逃がし先”を決めておくと効果が持続します。
監査で止める:ヒューマンエラー由来のロスを縮める
取り違えや重複出庫、入力誤りは、過剰在庫や返品不可在庫の温床になりがちです。バーコード照合や画像記録、ピッキングナビを備えた調剤監査システムを活用すると、現場のミスを体系的に減らせます。監査エビデンスが自動で残るため、期限接近品の優先消化や返品可否の判断材料としても機能します。
管理システムの導入
不動在庫を抑えるには、適切な在庫管理が欠かせません。ただし、手作業中心の運用は複雑になりやすく、人的コストも膨らみがちです。そこで在庫の把握から補充までをシステムで半自動化すると、作業負担を抑えつつ精度を高められます。入出庫や有効期限の管理が一元化されることで、発注の重複や期限切れの見落としといったヒューマンエラー由来の不動在庫も大幅に減少します。
レセコンに蓄積された過去処方データを活用して需要を予測し、適正在庫の算出や自動発注へ反映するタイプのシステムも一般的になりました。さらに、IoT機器と連携して入出庫を自動記録したり、期限接近や発注点割れをアラートで知らせたりする仕組みも選べます。店舗規模や処方構成、既存機器との連携要件に合わせて、運用負荷が少なく効果を実感しやすいものを選定してください。
まとめ
この記事では、デッドストックの原因や管理方法についてお伝えしました。デッドストックとは、仕入れたものの処方されずに使用期限まで保管され、最終的に廃棄される可能性が高い医薬品在庫です。
薬局では、薬剤師法に基づき処方箋を持参した患者の調剤を拒否できません。そのため、処方に対応できるように余分な在庫を抱えている薬局も多いのが現状です。
販売包装単位ごとの仕入れシステムや注文ミスなど、デッドストックが起きる原因はさまざま。在庫管理システムや加盟店同士で医薬品を取引できるマッチングサービス、買取専門業者への依頼など、デッドストック解消につながるサービスが普及しています。
デッドストックが薬局経営を圧迫して困っているという方は、マッチングサービスや一括買取サービスなどの利用を検討してみてはいかがでしょうか。
-
調剤ミス・クレーム・業務過多でお困りですか?
そのお悩み、PICKING GOが解決します! 引用元:https://cp.pickinggo.pdszero.com/
引用元:https://cp.pickinggo.pdszero.com/患者の待ち時間を短くできる
欠品の発生状況が具体的に把握できる
予製機能で在宅医療対応ができる
最大30日間の無料お試しサービスで失敗知らず
まずは無料でお試しください 公式サイトはこちら